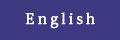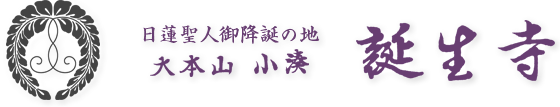10.弁天池と小湊弁財天
 仁王門から祖師堂へと向かう参道から右手を見ると、奇麗に整備された池があります。ちょうど宝物館の右側です。この池は弁天池といい、池辺にある小社には弁財天をお祀りしています。この弁才天は誕生寺の鎮守としてお祀りされたもので、小湊弁財天といいます。
仁王門から祖師堂へと向かう参道から右手を見ると、奇麗に整備された池があります。ちょうど宝物館の右側です。この池は弁天池といい、池辺にある小社には弁財天をお祀りしています。この弁才天は誕生寺の鎮守としてお祀りされたもので、小湊弁財天といいます。
弁才天は、略して弁天ともいい、大黒天や寿老人・恵比寿などと共に七福神の一つに数えられ、お正月の縁起物の宝船に乗った七福神の絵などにも見られます。その姿は楽器の琵琶を抱えた天女に描かれていますから、中国、或は日本の神様の様に思えますが、本来はサラスヴァティーというインドの女神で、河の神または農業神なのです。そして学問・智恵・弁舌・音楽などを司る神となり、仏教に採り入れられました。吉祥天と共に「金光明最勝王経」(きんこうみょうさいしょうおうきょう)などに説かれています。
小湊弁才天の尊像は、本師殿宝塔に安置する釈尊像を制作した西村房蔵氏が彫刻し奉納されました。岩の形をした台座に腰掛けて琵琶を弾く、大変にふくよかで優しい姿です。尊像そのものは、本堂の正面左側にある壇上の厨子に安置しています。池辺の社は、別宮として幣束(へいそく)を安置していますが、一間社持送破風造宮(いっけんしゃもちおくりはふうづくりみや)という建築形式をとった総欅造りです。平成元年8月10日、すべての工事が完了して遷座の法要が行われました。
 誕生寺に弁才天がお祀りされるのは、江戸時代に始まります。元禄16年(1703)11月、大地震とそれに伴う大津波によって誕生寺は大被害を受けました。弁才天が誕生寺にお祀りされたのは、この被害からの復興が進んでいた宝永4年(1707)のことです。当時の貫首であった26世日孝上人は、弁才天をお祀りするに至った経緯を「安房州小湊山鎮守弁天記録」1巻にまとめています。この記録によると、安房国長狭郡市川の出身で江戸に住んでいた瀧口政親が、自ら信仰していた霊験あらたかな弁才天の尊像を誕生寺に奉納しました。尊像は、丈は8寸ばかり、面貌はとても貴く、運慶の作であろうというものです。日孝上人は、尊像を誕生寺の鎮守として宝塔の側に小さなお堂を建てて安置し、5月18日に供養の法要を行ったのです。この弁才天は、その後火災にあって失われましたが、旧八大龍王堂の脇にあった池には近年まで弁才天がお祀りされていました。
誕生寺に弁才天がお祀りされるのは、江戸時代に始まります。元禄16年(1703)11月、大地震とそれに伴う大津波によって誕生寺は大被害を受けました。弁才天が誕生寺にお祀りされたのは、この被害からの復興が進んでいた宝永4年(1707)のことです。当時の貫首であった26世日孝上人は、弁才天をお祀りするに至った経緯を「安房州小湊山鎮守弁天記録」1巻にまとめています。この記録によると、安房国長狭郡市川の出身で江戸に住んでいた瀧口政親が、自ら信仰していた霊験あらたかな弁才天の尊像を誕生寺に奉納しました。尊像は、丈は8寸ばかり、面貌はとても貴く、運慶の作であろうというものです。日孝上人は、尊像を誕生寺の鎮守として宝塔の側に小さなお堂を建てて安置し、5月18日に供養の法要を行ったのです。この弁才天は、その後火災にあって失われましたが、旧八大龍王堂の脇にあった池には近年まで弁才天がお祀りされていました。この度の小湊弁才天の勧請は、この様な由来によって50万人講事業の一環として行われたものなのです。